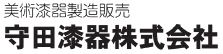▲中国・江蘇省の景色
こんにちは。ご覧いただき、ありがとうございます!
今回は、中国・江蘇省で行われた青少年交流派遣に参加し、現地で体験したことを少しご紹介したいと思います。なかでも、私にとって特別な経験となったのが、企業座談会での「山中漆器」についてのプレゼンテーションでした。初めての経験で、とても緊張しましたが、山中漆器の魅力を海外の方に伝えるために頑張りました!
国際舞台で語る「山中漆器」
今回の研修では、江蘇省の蘇州市や南京市を訪問し、最新の都市設計や技術開発、企業視察を行いました。
その中でも、特に印象に残っているのが企業座談会でのプレゼンテーションです。会場には、中国を代表する企業の方々、そしてグローバルに活動する研究者やビジネスパーソンが集まっていました。
そこで私は、勤めている守田漆器の商品である山中漆器について紹介する機会をいただきました。


▲この二つの資料を中国語に翻訳してプレゼンを行いました
「漆器って何?」からの挑戦

▲企業座談会の風景
山中漆器は、私の地元・石川県加賀市が誇る工芸品です。
しかし、中国の方々にとって「漆器」とはそもそもどんなものなのか、どこまで知られているのか…。そうした不安を抱えながらも、私は伝えたかったのです。
・木地のろくろ挽きという精緻な技術
・完成までに一年以上かけるお椀もあること
・山中は日本で最も漆器製造が盛んであること。つまり、山中が漆器製造においては世界一であること
与えられた2分間という短いようで長く感じた時間の中、身振りや写真を交えながら、伝統と現代が調和する魅力を全力で説明しました。
文化を紹介するということの難しさと喜び

▲南京師範大学
その後の南京師範大学でも自己紹介を交えて山中漆器について説明する機会をいただきました。南京師範大学は、日本のビルのような大学とは違い、伝統や趣を感じる神社やお寺のような建物が立ち並ぶ場所で、約4万人の生徒が通っていると教えてもらいました。交流した日本語学科の生徒の方からは、「実際に見てみたい」「どこで買えるのか」と声をかけていただきました。
その瞬間、「伝える」という行為の重みと喜びを実感しました。
一方で、自分の中に「もっと伝えられる言葉があったかもしれない」「技術や歴史について、もっと深く知っておくべきだった」という悔しさも残りました。でもそれは、私にとって次の学びへの大きなきっかけにもなりました。
伝統工芸を、世界とつなぐ架け橋に
漆器の美しさや、そこに込められた職人の想いは、国や言葉を超えて、誰かの心に響くものだと思います。
今回の経験を通じて、伝統文化は「守るもの」だけではなく、「伝えるもの」「広げるもの」でもあると感じました。
私は、山中漆器という地域の文化を、これからも学び、伝えていきたい。
そして、今後もし機会があるなら、もっと自信を持って、世界に向けて「日本の手仕事のすばらしさ」を発信していけたらと思います。
あとがき
中国での滞在は、技術的にも文化的にも大きな刺激を与えてくれるものでしたが、何よりも「人と人とが、文化を通じてつながる」瞬間を体験できたことが、私にとって最も大きな財産です。
山中漆器を世界に伝える最初の一歩として、今回のプレゼンや大学での交流が意味のあるものになっていたら嬉しいです。
そしてこれからも、そんな一歩を少しずつ積み重ねていけたらと思っています。
次回のブログでは、またQ&A方式で「生活実用編~機能面~」の漆器の魅力を伝えていこうと思いますので、ぜひご覧ください!
それでは~👋
Y.M